ついに始動!マシンインテリジェンス研究会の企業インタビュー
マシンインテリジェンス研究会が新たにスタートした企画、それが会員企業インタビューです。
記念すべき第1回は、バイスリープロジェクツ株式会社の菅野社長にご登場いただき、創業から現在までの歩み、そして技術へのこだわりについてじっくりお話を伺いました。
社名の由来は3倍?!

バイスリープロジェクツ株式会社は、1987年に菅野社長が創業。
今では社員約40名を抱える企業へと成長しました。
社名「バイスリープロジェクツ」には、「価値を3倍にする」という意味が込められているそうです。
遊び心と挑戦心が、社名からも感じられますね。
2017年には地域未来牽引企業に認定。
地域経済の発展を担う存在として、さらなる成長が期待されています。
地域未来牽引企業とは?
地域内外の取引実態や雇用・売上高を勘案し、地域経済への影響力が大きく、成長性が見込まれるとともに、地域経済のバリューチェーンの中心的な担い手、および担い手候補である企業
技術への情熱は受賞後も続く
同社の技術力を象徴するのが、表面欠陥検査ユニット「SSMM-1R」。
この開発によって、第7回ものづくり日本大賞・経済産業大臣賞優秀賞を受賞しました。
現在も複数の自動車工場で稼働しています。

さらに、AIを活用した新製品「SURF-AI(サーファイ)」の開発にも挑戦中。
従来の画像処理では難しかった塗装製品の外観検査を、リアルタイム(無停止)で検出可能にするAIモデルを構築しました。
ここには、研究会の会員企業である匠ソリューションズ株式会社のハード技術も活かされており、
高速画像処理や大量データ処理という課題に挑んでいます。
開発の現状と課題
現在、新製品開発はどのような状況なのか、菅野社長にお伺いしてみました。
 コーディネーター
コーディネーターAIを活用した新製品の開発は順調に進んでいますか?



それが、まだ販売に至っていないんですね。
展示会での技術展示は行っていますが、技術面の課題や製品化に向けたコスト面のハードルがあります



解決の糸口は見えてきましたか?



匠ソリューションズさんの協力もあり、技術的な蓄積はかなり進んでいます。着実に前に進んでいます
優秀賞を受賞しても歩みを止めず、次なる技術へ挑み続ける姿勢に胸を打たれます。
研究会での活動
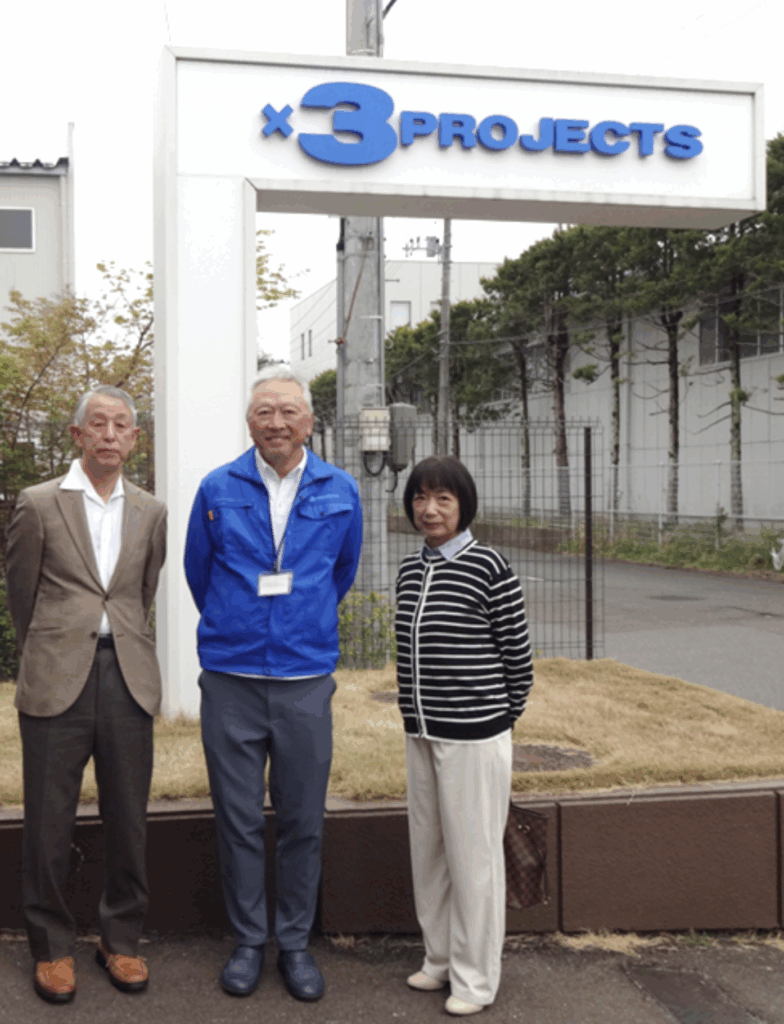
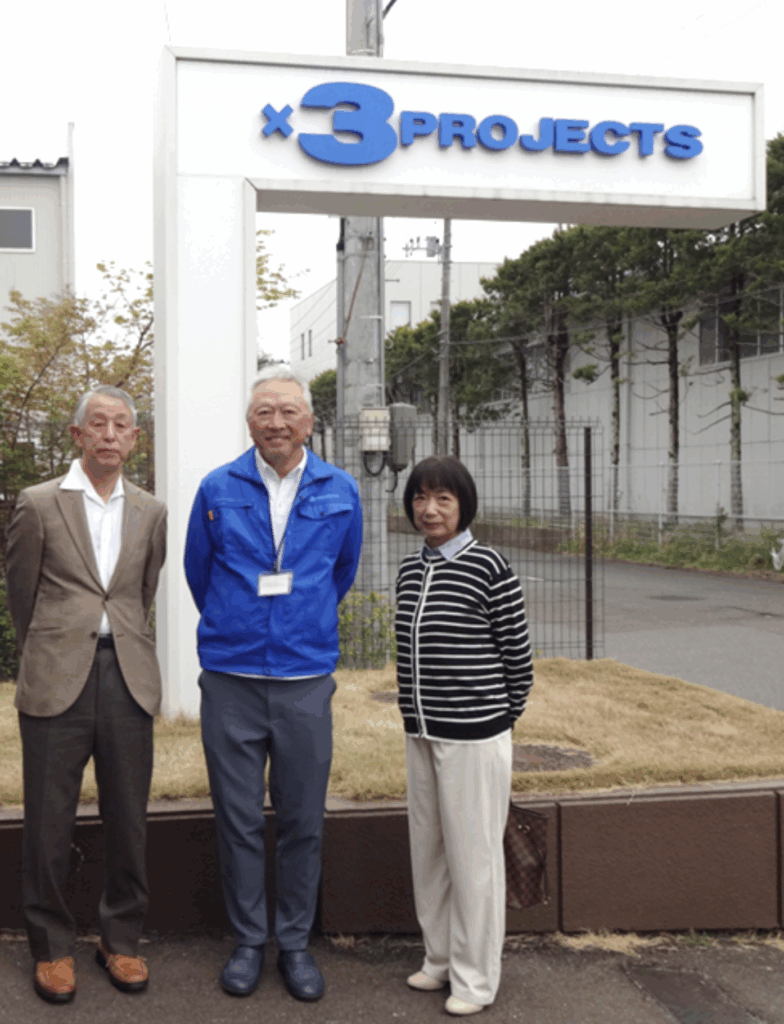
バイスリープロジェクツは、マシンインテリジェンス研究会の立ち上げ当初から参加しているチャーターメンバー。
特に東北大学IIS研究センターとのつながりを活かして、現場の課題解決や新しい技術づくりに挑戦してきました。
研究会では、会員同士の情報交換や技術発表の場を通じて、製品を使う立場の「川下企業」との共同開発も生まれています。
例えば、塗装製品の外観検査に関する相談をきっかけに、AIと高速画像処理を組み合わせた新しい検査モデルの開発がスタートしました。
さらに、IIS研究センターを通じて大学の先生を紹介してもらい、超音波を使った検査技術の相談や、AI開発のアドバイザー探しにも活用しています。
菅野社長は、「もっと川下企業の課題を研究会に持ち込みたい」と話します。
課題が増えれば、より実践的な成果が生まれ、会員全体のレベルアップにもつながるはずです。
今後の展望
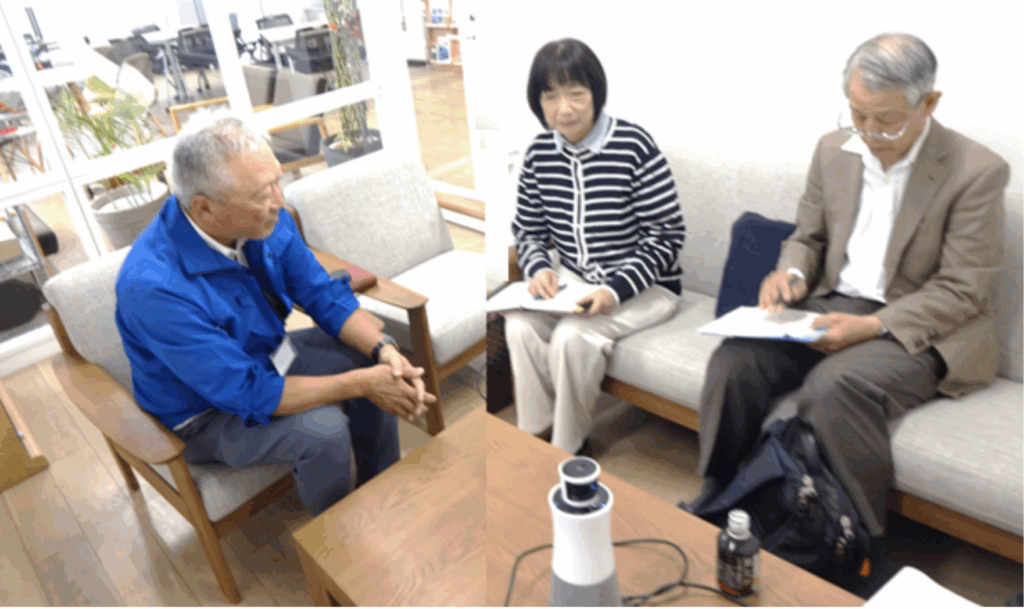
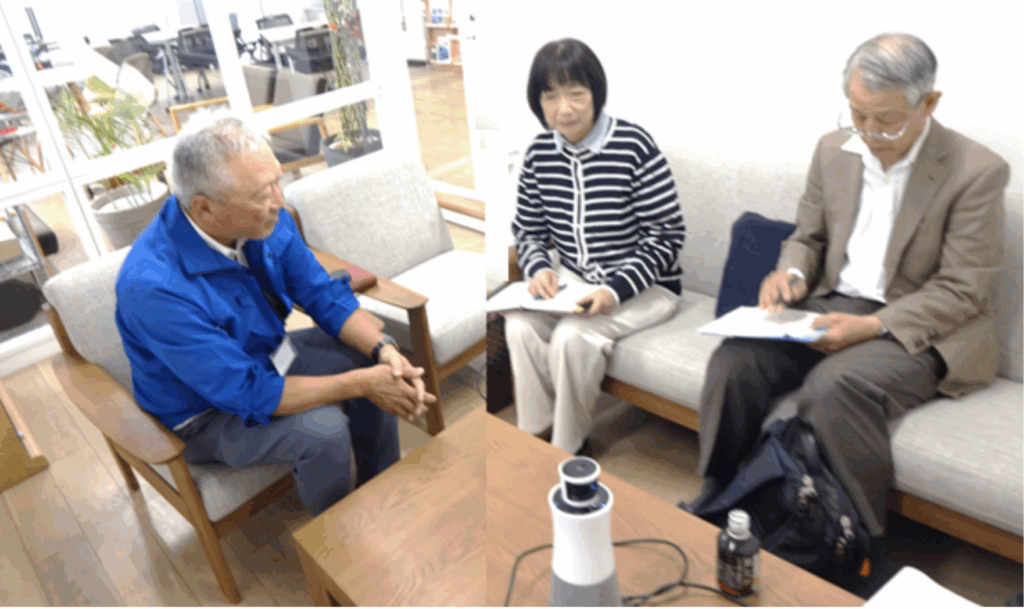
バイスリープロジェクツの企業理念は「技術による社会貢献」。
これからも画像処理技術を中心に、人の目で行っている検査を自動化し、現場の負担を減らしながら品質も守っていきます。
自動車、半導体、電子部品などの製造現場では、今も熟練作業者が目視で検査をしている工程がたくさんあります。
でも、人手不足や作業環境の厳しさを考えると、自動化はこれからますます必要になってくる分野です。
そうしたニーズに応えるため、
- AIモデルをもっと正確に、もっと速くすること
- 実際の現場そっくりなCGデータを作って効率よく学習させること
- 川下企業や研究機関とのつながりを強めて、実用化と普及を進めること
こうした取り組みを続けていきます。
「現場で本当に役立つ技術」を届けながら、地域の産業や日本のものづくりの未来を支えていく――。
そんな思いで、これからも挑戦を続けます。


